顧客の7割が評価する「的確な回答」─問合せの意図を汲み取る3つの技術で成約率が変わる
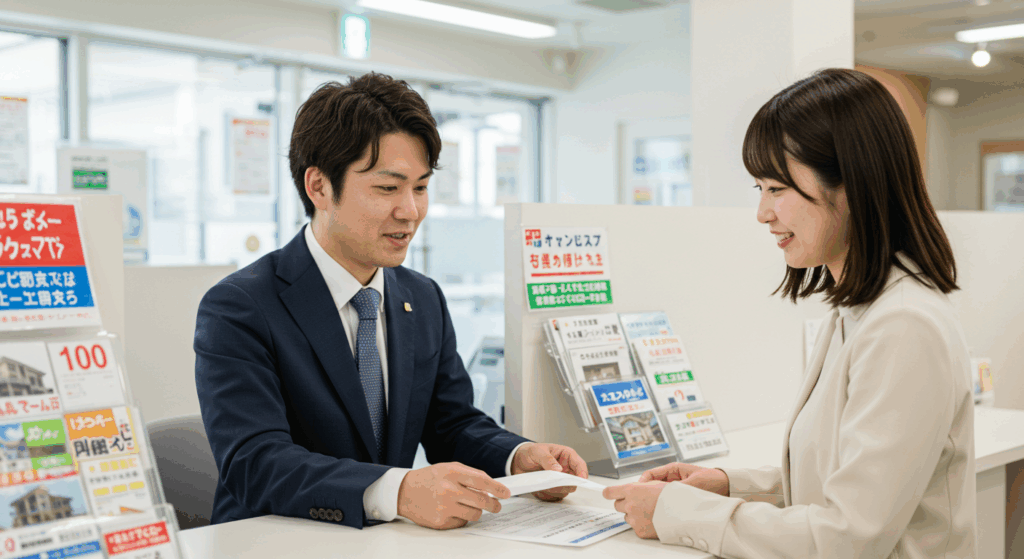
「その物件はもう埋まっています」「詳細は来店いただければ」─顧客からの問合せに、こうした定型的な返答をしていないだろうか。不動産情報サイト事業者連絡協議会(RSC)の最新調査によれば、問合せへの対応品質が契約の成否を分ける決定的な要因になっている。特に注目すべきは、顧客の14.4%が「問合せへの回答が的を射ていなかった」ことを不満要因として挙げている一方で、「的を射た回答」を受けた顧客の満足度は極めて高いという事実だ。最初の60分間で顧客の心をつかむか逃すか。その分岐点となる「問合せ対応力」を、データと実践的手法から紐解いていく。
なぜ「的はずれな回答」が顧客を遠ざけるのか
問合せ対応が成約を左右する時代
2024年の不動産市場では、顧客行動に顕著な変化が見られる。RSCの調査データが示すのは、物件契約者が問合せた不動産会社数の平均が2.7社(前年比0.5社減)、問合せ物件数が平均8.9物件(前年比2.2物件減)と、いずれも直近10年で最少となった事実だ。
これが意味するのは、顧客が「あらかじめ絞り込んだ上で問合せている」という現実である。つまり、一度の問合せに込められた期待値は以前よりも遥かに高く、その期待に応えられなかった場合の離脱リスクも大きくなっているということだ。
数字が物語る「的確な対応」の価値
同調査で特筆すべきは、顧客満足度に関する以下の数値だ:
- 不満要因として「問合せへの回答が的を射ていなかった」:14.4%
- 満足要因として「問合せへの回答が的を射ていた」:24.0%
- 最大の満足要因「問合せに対するレスポンスが早かった」:69.5%
これらのデータから読み取れるのは、スピードと的確さの両立が求められているという事実だ。早いだけでは不十分であり、顧客の質問の背景にある真の意図を理解し、それに応える回答が必要とされている。
顧客をイライラさせる「3つの的はずれパターン」
パターン1:表面的な質問にしか答えない
「この物件の日当たりはどうですか?」という問合せに対し、「南向きです」とだけ答える。これは典型的な的はずれ回答だ。
顧客が本当に知りたいのは、単なる方角ではない。「朝から洗濯物が乾くのか」「在宅勤務で日中部屋にいるが快適か」「西日で夏場暑くないか」といった、生活実感に基づいた情報を求めている。
質問の裏側にある生活シーンを想像できない対応は、顧客に「この担当者は自分のニーズを理解していない」という印象を与えてしまう。
パターン2:マニュアル的な回答で逃げる
「周辺環境について教えてください」という問合せに、「スーパーは徒歩5分、駅まで徒歩10分です」と物件概要に書いてある情報を繰り返すだけのケースも多い。
顧客が知りたいのは、数字以上の情報だ。「深夜営業のスーパーがあるか」「子供の通学路の安全性は」「騒音が気になる幹線道路は近くにあるか」─こうした具体的な生活情報を求めている。
大手不動産ポータルサイトに掲載されている基本情報は、顧客自身がすでに確認済みである。問合せをするということは、そこに書かれていない情報を知りたいというサインなのだ。
パターン3:顧客属性を無視した提案
「ファミリー向けの広めの物件を探しています」という問合せに対し、「こちらの1Kも人気ですよ」と的外れな提案をする。あるいは、「予算は10万円以内で」と明示しているのに「少し予算を上げれば良い物件が」と押し付けがましく勧める。
顧客の条件を無視した提案は、信頼を失う最短ルートだ。RSC調査でも「問合せをしていない(希望していない)物件を必要以上にすすめられた」が不満要因の上位にランクインしている。
問合せの意図を正確に汲み取る「3つの実践技術」
技術1:「なぜ」を3回掘り下げる質問力
的確な回答の前提となるのは、的確な質問だ。顧客からの問合せに対し、すぐに答えを返すのではなく、まず背景を探る質問を投げかける。
実践例:
- 顧客:「ペット可の物件はありますか?」
- 担当者:「承知いたしました。どのようなペットをお飼いですか?」
- 顧客:「小型犬です」
- 担当者:「お散歩の頻度や時間帯はいかがでしょうか? 周辺環境も考慮してご提案できればと思います」
この3段階の質問により、単に「ペット可」というだけでなく、「朝夕の散歩がしやすい公園近くの物件」や「ペット足洗い場がある物件」など、真のニーズに合致した提案が可能になる。
技術2:ライフスタイルを可視化する対話術
顧客の質問から、その人の生活パターンを立体的に理解する力が求められる。これは単なるヒアリングではなく、顧客自身も気づいていない潜在ニーズを引き出す技術だ。
効果的な質問例:
- 「お休みの日はどのように過ごされることが多いですか?」
- 「ご自宅ではどの時間帯に一番長く過ごされますか?」
- 「在宅勤務の頻度はいかがでしょうか?」
- 「今のお住まいで気に入っている点、改善したい点は?」
これらの質問を通じて、顧客が重視する要素が「静かな環境」なのか「利便性」なのか、「収納力」なのか「開放感」なのかが明確になる。そして、物件の特徴をこの優先順位に沿って説明することで、的確な回答となる。
技術3:「でも」で終わらせない代替案提示力
希望条件に完全に合致する物件がない場合、「該当物件はありません」で終わらせるのは機会損失だ。顧客が求めているのは「諦める理由」ではなく「次善の選択肢」である。
代替案提示の実践:
- 「ご希望の駅徒歩5分以内の物件は現在空きがございませんが、一駅隣の○○駅であれば急行停車駅で通勤時間はほぼ変わらず、徒歩3分の物件がございます」
- 「3LDKで10万円以内は厳しいのですが、2LDK+広めのリビングで収納力を確保した物件でしたら、ご家族構成的にも十分機能するかと存じます」
重要なのは、なぜその代替案が顧客にとって価値があるのかを、先ほど掘り下げた顧客のライフスタイルや優先順位と結びつけて説明することだ。
デジタル時代における問合せ対応の新常識
「最初の60分」が勝負を分ける
RSC調査では、住まい探しから契約までの期間が短期化傾向にあり、特に「2週間未満」の割合が直近10年で最も高くなっている。これは、意思決定スピードが加速していることを示唆している。
顧客は大手不動産ポータルサイトで膨大な物件情報に触れ、比較検討を重ねた上で問合せをしてくる。その最初の接点である問合せ対応で、「この担当者は信頼できる」「自分のことを理解してくれる」と感じてもらえなければ、次の候補に移られてしまう。
「最初の60分」とは、問合せ受信から初回返答までの時間と、その回答の質を指す。この60分で示せる対応力とプロフェッショナリズムが、その後の商談につながるかどうかを左右する。
オンライン時代の信頼構築
非対面での接客が増える中、対面以上に「的確さ」が重要になっている。同調査では、IT重説やオンライン接客への関心が年々高まっている一方で、だからこそ対応品質への期待も高まっている。
画面越しのやり取りでは、表情や雰囲気だけで信頼関係を築くことが難しい。顧客が判断材料とするのは、返答内容の的確さ、情報の充実度、そして顧客理解の深さだ。
組織として問合せ対応力を高める仕組み
ナレッジ共有が競争力を生む
的確な回答ができる担当者とそうでない担当者の差は、情報量と経験値の差に起因することが多い。これを組織全体の力に変えるには、ナレッジ共有の仕組みが不可欠だ。
効果的なナレッジ共有の例:
- よくある質問と優良回答事例のデータベース化
- 成約につながった対応事例の定期的な共有会
- 地域特性や物件特性に関する情報の一元管理
- 顧客タイプ別の対応ポイント集
こうした仕組みがあれば、経験の浅い担当者でも、ベテランと同等の対応品質を実現できる。
フランチャイズ本部のサポート価値
大手フランチャイズ本部が提供する価値の一つが、こうしたナレッジとノウハウの体系化だ。個店では蓄積が難しい膨大な成功事例や対応マニュアル、トレーニングプログラムを活用することで、組織全体の対応力を底上げできる。
また、業界動向や顧客ニーズの変化に関する情報提供、最新のITツール導入支援なども、フランチャイズ本部ならではのサポートだ。これにより、個店が独自に対応するよりも効率的に高品質なサービスを実現できる。
まとめ:「的確な一言」が未来の収益を作る
顧客が問合せをする瞬間、そこには「この物件で新生活を始められるかもしれない」という期待と、「本当にこの担当者に任せていいのか」という不安が同居している。
その心理に応えるのが、顧客の質問の背景を理解し、真のニーズに応える的確な回答だ。RSC調査のデータが示すように、的を射た回答ができる担当者は顧客満足度を高め、結果として成約率向上につながる。
問合せ対応は、単なる情報提供ではない。それは顧客との信頼関係構築の第一歩であり、あなたのプロフェッショナリズムを示す最初の機会だ。
「なぜ」を3回掘り下げる質問力、ライフスタイルを可視化する対話術、そして代替案を提示する柔軟性。この3つの技術を磨くことで、顧客をイライラさせる「的はずれな回答」を、成約につながる「的確な一言」に変えていくことができる。
デジタル化が進み、顧客の選択肢が増え続ける今だからこそ、人間にしかできない深い顧客理解とコミュニケーションが、不動産賃貸仲介業における最大の差別化要因となる。最初の60分を制する者が、顧客の信頼を勝ち取り、持続的な成長を実現できるのだ。
※本記事は不動産情報サイト事業者連絡協議会(RSC)「不動産情報サイト利用者意識アンケート2024」のデータを参考に作成しています。







